\堂々と外食に行きたいから今こそ取り組もう!/

子どもの箸の持ち方が気になるけど、矯正箸はよくないって聞く。と気になってませんか?
結論:やらないよりは、絶対にやった方がいいです。
実は我が家も、小2の娘の箸の持ち方がよろしくなく…。矯正の仕方を調べたことが今回の記事のきっかけです。箸の持ち方は一生のマナー。これが原因でいじめに発展するかも。と考えるとなんとしても今正しておきたい…。(この話はまとめに書くのでよかったら最後まで読んでください(^^;))
矯正箸も、使い方さえ間違えなければ頼れるサポーター。
「ダメ!」と決めつけるより、短い期間でも上手に取り入れていくことをおすすめします!
この記事では、どうやって子どもに正しい持ち方を身につけさせていけばいいかを、分かりやすく紹介します。
\我が家はこれで実践!やっぱり木がいい/
箸の持ち方を改善する|ステップアップリスト
小学校に入る前に、きちんとした箸の持ち方を身につけておくと、給食の時間でも困らずに済みますよ。親としても「ちゃんと持ててるかな?」と気になるところ。
そんなときに役立つ、家庭でのステップアップ練習法をご紹介します!
- スプーンの持ち方を見直してみる(鉛筆持ち=ペングリップができてる?)
- 鉛筆の持ち方が正しいかチェックしてみる
- お手本として大人が正しく持てているか確認する
- 箸以外(豆・ビーズ・スポンジなど)を使った遊びも取り入れてみる
- おしゃれな(フォーマルな)喫茶店や飲食店に連れて行く
娘のことをよく見てみると、まず鉛筆の持ち方がおかしいことに気づきました(*_*)ぜひお子さんのスプーンや鉛筆の持ち方もチェックしてみてください!
\小学生低学年は18cmがおすすめ/
矯正箸がよくないと言われる理由
便利そうに見える矯正箸ですが、「よくない」と感じている親御さんの声も少なくありません。その理由を、よくある4つの視点から解説していきます。
① 正しい持ち方が身につかないこともある
矯正箸は「形を覚えるための道具」としては優秀ですが、それだけに頼ると逆に「考えなくても持てる」クセがついてしまいます。
子どもが「なぜこの形なのか」「どう指を動かせばいいのか」といった感覚を養えないまま使い続けてしまうケースも多いです。結果として、矯正箸を卒業した後に「普通の箸ではうまく使えない」ということに。
「形は真似できるけど、感覚がついてこない」――これが、矯正箸の落とし穴とも言えます。
② 本人の感覚が育ちにくい
正しく持つためには、箸の微妙な動きや力加減を自分の指先で感じ取ることが大事。
ところが、矯正箸はその部分を道具が代わりにやってくれるので、子ども本人の感覚が育ちにくくなってしまいます。
特に、力加減が必要な細かい動作――例えば「やわらかい豆をつまむ」とか、「すべらないように持ち上げる」といったときに、その差が出やすいんです。
あくまで“自分の手で考える”ことが大切なんですね。
③ 市販の矯正箸はサイズが合わない場合も
矯正箸は年齢ごとにサイズが出ているものの、実際の手の大きさには個人差があります。
「サイズが少し合ってないだけで、持ちにくくて逆に変なクセがついた」という声もあります。しかも、多くの矯正箸はプラスチック製で滑りやすかったり、重かったりして、逆に扱いづらいことも。
もし使うなら、サイズや素材にこだわって、短期間だけのサポートアイテムとして使うのが良さそうです。
④ 親の「任せっぱなし」になるリスク
「矯正箸を使わせてるから、もう大丈夫でしょ」と思ってしまうのも危険です。
大人がチェックせずに放置していると、矯正箸を使っていても、全然違う持ち方になっていた…なんてことも。
矯正箸はあくまで補助的なものと考えて、「一緒に確認する」「定期的に普通の箸でも試してみる」など、親のフォローが必要です。
まとめ|矯正箸を上手に活用して正しい持ち方を習得
矯正箸がよくないと言われる理由には、「感覚が育ちにくい」「道具に頼りすぎるリスク」などがあります。でも、ちゃんと使い方を意識すれば、決して悪い道具ではありません。
子どもに合ったサイズを選び、親がそばで見守りながら使うことで、むしろスムーズに正しい箸の持ち方へつなげることができます。
やらないより、やったほうが確実に前進です。
【娘の話】
とても活発な我が娘。自己肯定感を下げないように褒めることを大事にしてるつもりでも、叱ることの方が多く…。共働きだったこともあり、朝も夜も孤食が多め。それでも保育園時代は「食べる=寂しい」にならないように食事中に一日のお話を聞くなどを重視して、最低限の「食べ方」だけは注意するようにしてました(皿を持つ、犬食いしないなど)。
小学2年生になったある日友達から「〇〇ちゃん、お箸の持ち方変だよ」と指摘されたと少し悲しそうに言ってきた!!
これはチャンスだ!と思い、厳しくも指摘するようにしましたが全然改善されない(T_T)まさか鉛筆の持ち方からおかしいとは思ってなく、ちょっとショックでした(^^;)
「〇〇君からご飯誘ってもらえなくなるよ」や実母、義母、いとこも召喚して声掛けに協力してもらっても、不機嫌になるばかりでお手上げ…。これは困った。
ということで、ついに矯正箸を使うことにしました。結果、2週間ほどでマシに!!
真ん中にピアノが置いてあって、昔ダンスパーティーが行われていたような超フォーマルな喫茶店で食事をしたところ、本人の自信にも繋がりホッとしました(*´ω`*)そしてなんだかんだ親も楽しみました。フォーマルな喫茶店は保育園生にはまだ早いから、取り組んだのが小学生でよかったかも?!笑
お箸の持ち方やマナーは一生のもの。矯正箸のデメリットを聞いても、それが原因でいじめに発展したら…と思うとその方がイヤです。
これからも向き合っていこうと思います。(きっかけをくれたMちゃんありがとう)
皆さん子育てお疲れ様ですm(_ _)m

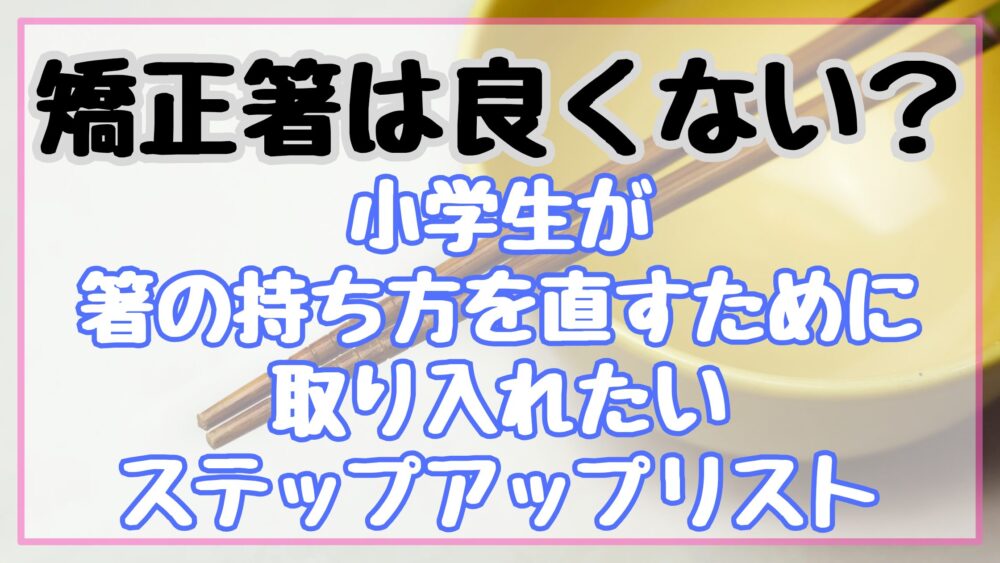



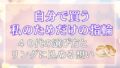
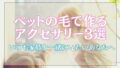
コメント